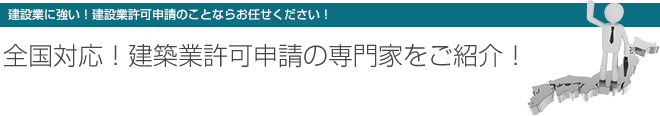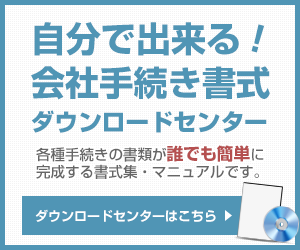建設業と労災保険
建設業と労災保険
労働基準法では、業務災害や通勤災害、業務中の負傷や病気、死亡など、事業所側に落ち度がなかった場合でも、本人又は遺族に対して補償する義務があるとしています。
こういった災害補償の義務を確実に履行できるように、事業者等に労災保険への加入を義務付けています。
労災保険に加入するのは?
労働者(パート、アルバイト、期間雇用、日雇、外国人すべてを含む)を1人でも雇用する事業所が対象となります。
補償は誰が行うの?建設業の場合は、元請業者。
通常、災害補償の責任は、雇い主が負担することになっていますが、建設業のような請負事業は元請業者にあると労働基準法では規定されています。
工事の規模にかかわらず、下請の労働者を使用して発生した現場での労働災害は、元請事業者の労災保険を使用して補償します。
下請事業者でも労働者を雇用していれば労災保険に加入していますが、
請負契約のもとで元請・下請・孫請と複数の事業者が同じ現場で作業している中で労働災害が発生した場合については、
使用者としての責任が曖昧になるのを防止し、また、被災した労働者を迅速に保護するために、このような規定が例外で定められています。
労災保険の計算と納付
労災保険料は全額事業主が負担することになっています。
毎年4月1日から翌年3月31日までを保険年度とし、年度の終了までの保険料を概算で計算し毎年6月1日から7月10日までの間で見込み払を行います。
年度終了時に実際の保険料を確定し、過不足額を申告して精算します。
計算方法は、
保険料 = 保険年度に支払われた賃金総額 × 労災保険率
です。
請負事業の計算方法
建設業者などの請負事業の場合は、元請負人が事業主とされるため、保険料は下請業者に使用される労働者の分も含めて計算しなければなりません。
請負いのため賃金の総額が正確に計算することが困難な場合は、特例の計算方法があります。
賃金総額 = 請負金額(消費税込)× 労務費率
事業主の労災加入
個人事業主や一人親方、家内労働者などは労働基準法の労働者ではないため、労災保険の対象外となります。
しかし、業務の状況や災害の発生率から見て保護が必要とする場合、特別加入制度が設けられています。
この特別加入制度は労働者と補償内容が若干異なります。
- 特別加入をすることで労働者と同じ保証を受けることができますが、経営者として活動中に発生した災害は補償の対象となりません。
- 給付の算定基礎となる給付基礎日額は3,500円~20,000円の範囲で加入者が希望する額を考慮して所轄の労働局長が定めます。
建設業における労災保険未加入対策として、工事現場では労災保険加入の掲示が義務付けられており、未加入業者への現場入場を禁止するなど、厳しく指導されています。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら
建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!
北海道・東北 エリア
-
 経営事項審査に強い! 福島県
経営事項審査に強い! 福島県
行政書士近藤事務所 -
 北海道
北海道
行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
関東 エリア
-
 埼玉県
埼玉県
Ican行政書士事務所 -
 神奈川県
神奈川県
ATSU行政書士事務所 -
 茨城県
茨城県
久保行政書士事務所 -
 神奈川県
神奈川県
ミウラ行政書士事務所 -
 長野県
長野県
COCORO行政書士法人 -
 神奈川県
神奈川県
Y&Y行政書士事務所 -
 神奈川県
神奈川県
湘南労働法務事務所 -
 東京都
東京都
行政書士法人GOAL
北陸 エリア
-
 石川県
石川県
行政書士小山内合同事務所
東海 エリア
-
 愛知県
愛知県
行政書士伊藤りょういち事務所 -
 岐阜県
岐阜県
行政書士大口事務所 -
 静岡県
静岡県
行政書士遠山法務事務所 -
 三重県
三重県
行政書士事務所ナデック -
 経営事項審査に強い! 愛知県
経営事項審査に強い! 愛知県
行政書士今枝正和事務所 -
 愛知県
愛知県
織田行政書士事務所 -
 愛知県
愛知県
TSパートナー行政書士事務所
近畿 エリア
-
 奈良県
奈良県
行政書士西口労務パートナーズ -
 兵庫県
兵庫県
ルリエ神戸行政書士事務所 -
 兵庫県
兵庫県
行政書士門脇事務所 -
 大阪府
大阪府
行政書士オフィスN
九州・沖縄 エリア
-
 長崎県
長崎県
行政書士井手法務事務所 -
 大分県
大分県
べっぷ・ふくおか行政書士法人 -
 長崎県
長崎県
シーガル法務事務所 -
 熊本県
熊本県
行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
信頼の実績!建設業許可申請.comなら安心
PICK UP! 専門家
おすすめコンテンツ - Category
- 特集記事 – TOPICS!! (17)
- 建設業許可申請手続き (81)
- その他の工事業登録・届出について (3)
- 会社設立(法人成り)と建設業許可について (1)
- 建設工事の種類とそれぞれの許可要件 (28)
- 建設業に関連する各種資格・試験・講習情報 (7)
- 解体工事許可について (9)
- 経営事項審査(経審) (45)
- その他審査項目(社会性)の評価 (8)
- 指名願い(入札参加資格審査申請) (1)
- 建設業許可の更新&変更手続き (10)
- よくあるご質問・Q&A集 (64)
- 個人事業と建設業許可Q&A (3)
- 営業所に関するQ&A (2)
- 建築・土木一式工事に関するQ&A (3)
- 建設業許可の変更・更新手続きに関するQ&A (9)
- 建設業許可申請手続きに関するQ&A (23)
- 社会保険・労働保険に関するQ&A (6)
- 経営事項審査・公共工事に関するQ&A (4)
- 経営業務管理責任者・専任技術者に関するQ&A (8)
- 給与に関するQ&A (2)
- 請負契約に関するQ&A (4)
- 一人親方について (13)
- 雇用・労災・健康保険関係 (22)
- 社会保険に未加入の事業所様へ (11)
- 行政処分・処分事例・立入検査などについて (7)
- 会社再編 (7)
- 建設業の契約書・約款等について (1)
- 税金・資金調達・お金 (54)
- 建設会社が入れる保険 (2)
- 社長なら知っておきたい【税金・お金のこと】 (21)
- 税理士との付き合い方 (3)
- 税理士に頼める仕事 (7)
- 融資・資金調達・補助金・助成金 (20)
- 知っておきたい建設用語! (18)
- 建設業者をサポートする専門家 (9)
- 会社変更手続きサポートのご案内 (1)
- 自分でできる!変更登記キットのご案内 (1)
- 株式会社設立をお考えの業者様へ (12)
- その他の許認可手続きについて (28)
- 産業廃棄物処理業許可申請 (24)
- 産業廃棄物許可Q&A (5)
- 農地の転用手続き (4)
- 産業廃棄物処理業許可申請 (24)
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
- 特集記事 – TOPICS!! (17)
建設業許可手続き
- 建設業許可申請手続き (34)
- 経営事項審査(経審) (36)
- 建設業許可の更新&変更手続き (10)
- その他審査項目(社会性)の評価 (8)
- 指名願い(入札参加資格審査申請) (1)
- 建設工事の種類とそれぞれの許可要件 (28)
- その他の工事業登録・届出について (3)
よくあるご質問・Q&A集
- 経営業務管理責任者・専任技術者に関するQ&A (8)
- 個人事業と建設業許可Q&A (3)
- 営業所に関するQ&A (2)
- 建設業許可の変更・更新手続きに関するQ&A (9)
- 建築・土木一式工事に関するQ&A (3)
- 建設業許可申請手続きに関するQ&A (23)
- 社会保険・労働保険に関するQ&A (6)
- 経営事項審査・公共工事に関するQ&A (4)
- 給与に関するQ&A (2)
- 請負契約に関するQ&A (4)
一人親方
- 一人親方について (13)
社会保険・労働保険
- 雇用・労災・健康保険関係 (22)
- 社会保険に未加入の事業所様へ (11)
建設業の契約書・約款について
- 建設業の契約書・約款等について (1)
建設業許可と法人成り
- 会社設立(法人成り)と建設業許可について (1)
- 株式会社設立をお考えの業者様へ (12)
専門家の活用
- 建設業者をサポートする専門家 (9)
- 自分でできる!変更登記キットのご案内 (1)
- 会社変更手続きサポートのご案内 (1)
行政処分など
税金・資金調達・お金
- 融資・資金調達・補助金・助成金 (20)
- 社長なら知っておきたい【税金・お金のこと】 (21)
- 税理士との付き合い方 (3)
- 税理士に頼める仕事 (7)
- 建設会社が入れる保険 (2)
建設業許可と会社再編
- 会社再編 (7)
用語集
- 知っておきたい建設用語! (18)
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
- 産業廃棄物処理業許可申請 (19)
- 農地の転用手続き (4)
Copyright (C) 2026 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。